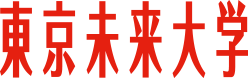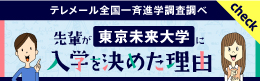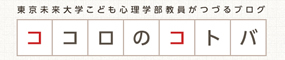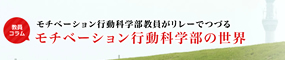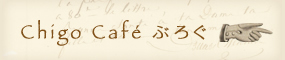プロジェクト紹介
- 新しいアクティブ・ラーニングのかたち
- 仲間と一緒だから、踏み出せる。チャレンジしたから、自信になる。私たちの表情が、その証拠です。
PROJECT
01
MIRAIFES.
ミライフェス
開学以来の伝統である未来祭と三幸フェスティバルを統合した一大プロジェクト
DAY1 は<こどもから大人まで楽しめる企画&出展>として、DAY2 は<スポーツと表現の祭典>として開催。
開学以来の伝統である未来祭と三幸フェスティバルを統合した一大プロジェクト
DAY1 は<こどもから大人まで楽しめる企画&出展>として、DAY2 は<スポーツと表現の祭典>として開催。


みんなで手作りする、
エンタテインメント・ビジネスです。
- こどもから大人まで楽しめる企画&出展
- MIRAI FES DAY1.は地域密着型イベント。学生やその家族、友人はもちろん、地域の方々、家族連れ、かわいい子どもたちなど、幅広い年齢層の方が来場されます。すべての方々が楽しめるアットホームなおもてなしに満ちた一日になるよう、学生たちは知恵をしぼり、遊び心を発揮します。事前に企画運営費獲得のための企画プレゼンテーションがあり、審査により資金配分が決まるという仕組み。エンタテインメント型のサービスモデルを練り上げ、運営チームをマネジメントし、どう利益を上げるかという収益モデルを築く絶好のトレーニングになります。
- STUDENT'S
VOICE - 全員が初めての経験。
未来大らしい結束で、やり遂げました。
未来大の二大看板だった未来祭と三フェスを1つのプロジェクトとして開催するMIRAI FES.の舞台裏は予想をはるかに超えて大変でした。私は企画部で初のリーダー役。DAY1のステージも、DAY2のオープニング、フィナーレもすべて企画部の仕事。タスクの多さに唖然としました。気づけばテーマソングの周知は締切ギリギリ。「企画部は本番予定通りにいかないことがたくさんあるよ」と言われていましたが、本当にその通り。中夜祭では歌の途中で音が止まるハプニング。DAY1当日には、タレントさんのステージまでの移動経路に不備があるとマネージャーさんから指摘され実行委員総動員で緊急対応。期間中、ずっと緊張が続く企画部でしたが、企画が終わるたび、担当メンバーはやり切った達成感で号泣していました。みんな初めてで不安だったと思うのですが、来てくださったお客様を楽しませたいという一心で、互いに助け合い最高のステージを作る。未来大らしい結束を見ることができたことが一番の思い出です。


こども保育・教育専攻4年
埼玉県立 深谷第一高等学校出身
小山 瑞貴さん


チーム一丸となって、競います。
じーんときます。涙がこぼれます。
- スポーツと表現の祭典
~学部学年を超えて、チームビルディングを学ぶ - MIRAI FES.DAY2は、学部学年を超えた団を編成し、団長のリーダーシップの下、「競技」「パフォーマンス」「応援」の3つの取り組みに参加します。チームビルディングやプロジェクトの企画・運営の方法、何より仲間と協力し、結束しあうことから生まれる創造力を学びます。また、保育・教育現場には必ず運動会などのイベント型学習の機会があるため、どうすれば子どもたちをリードし、イベントを成功に導くことができるのかを学ぶ必要があります。保育者・教育者を目指す学生にとって、この経験は将来に活きる学びになります。
- STUDENT'S
VOICE - 不可能だって、可能にできる。
応援団の勇姿を見て、涙が出ました。
応援団3団の意向を聞きながら、一つの舞台をまとめ上げるのが裏方である私たち応援団部の役割。たとえば、全員でのあいさつが少しずれるだけで、緊迫した空気が崩れてしまうのが応援団の怖いところ。練習方法や注意点を伝えたり、悩みや不安も聞きつつ伴走します。直前の練習、あまりに疲弊しきっている団員たち。とても心配でした。本番当日、応援団が走り出す合図となる最初の太鼓は私が叩きました。「あなたが送り出さなくて誰が送り出すの?」とCAの先生に言われて、頑張れと願いを込めてバチを握りました。私の心配を吹き飛ばすかのようなすごい迫力の演舞。涙が止まりませんでした。終わった後に「終わっちゃうのが寂しいです」とお礼を言いに来てくれた1年生がいました。完成度も大事、でも一人ひとりの充実度がもっと大事。未来大の伝統、みんなの心に残すことができて嬉しいです。


心理専攻4年
私立NHK学園高等学校出身
武熊 美樹さん
PROJECT
02
キャンパスクルー
大学の魅力を伝える
オープンキャンパスの在学生スタッフ
大学の魅力を伝えるオープンキャンパスの在学生スタッフ

高校生に大学生活のホンネを伝える、
実感伝達者です。
「笑顔で高校生を迎えたい。質問にはていねいにホンネで答えて、未来大の良さ、大学生活の楽しさを伝えたい」という、アツい想いで活動をしているキャンパスクルー。キャンパスクルーの役割は、高校生と一緒にキャンパスを歩きながら、施設を案内したり質問に答えたりすること。大学選びは、基準が難しい。だからこそマニュアルではなく、学生本人の実感を伝えることで、高校生に未来大の良さを発見してもらいたいと思っています。
- STUDENT'S
VOICE - 飾らない等身大の自分だと
高校生との距離も近くなりやすい。
「雰囲気はいいけど、伝えたいことがぼんやりしている」「最初に言ったことと結論が違う」CAの先生のフィードバックは手厳しい。自信がないところが、全部バレてしまいます。曖昧な回答をしていると、高校生のためにならない。一つひとつノートに書いて徹底しました。年間50回以上開催するので、何度も特訓できるのがクルーのいいところ。ある日、保護者の方への説明会後にCAの先生から「小山100点!」と言ってもらえました。以前は高校生の前でボロを出さないよう背伸びしていたのですが、最近は飾らない自分で接することができるように。高校生との心の距離が近くなった気がします。


心理専攻4年
神奈川県立 逗子高等学校出身
小山 琉那さん
PROJECT
03
スタートアップ
セミナー
社会の基礎を学べる新入生研修
社会の基礎を学べる新入生研修

はじめが肝心。
4年間を濃くする新入生研修。
スタートアップセミナーとは、入学時に行われる新入生研修です。4年間の目標を立て、大学生活をスタートさせます。「大学=プレ社会人期間」と位置づけ、社会の基礎となる挨拶やマナーを最初に学びます。将来あなたが保育者や教育者はもちろん、どのような仕事につく場合でも挨拶の重要性を知ることは、とても大切です。挨拶ができない先生が子どもたちに指導するのは難しいですよね。“スタセミ”はそんな社会の入口です。
- STUDENT'S
VOICE - 新入生を温かく迎え入れる伝統。
しっかりつないでいきたい。
入学式もスタートアップセミナーもない。私が入学した2020年は本当に寂しい春でした。自分達ができなかったことを後輩に伝えたいと先輩スタッフ“オリター”に。リーダーに任命されたものの、自分自身が経験したことがないということが課題の一つでした。知らない私にスタセミを教えてくれた後輩たち。本当に助けられました。みんなで頑張って考えたスリーヒントクイズというアイスブレイクも大盛り上がり。初めは緊張していた新入生の顔がみるみる明るく。終了後に「来年、オリターやりたいです」と声をかけてくれた1年生がいました。新入生を温かく迎え入れる未来大の伝統、未来につなげてほしいです。


心理専攻4年
千葉県立 柏の葉高等学校出身
山﨑 遥菜さん
PROJECT
04
こどもみらい祭
小学生参加型の地域連携プロジェクト
小学生参加型の地域連携プロジェクト

子どもたちと触れ合いながら、
子どものためのお祭りをプロデュース。
大学近隣の小学生と地域連携推進委員会の学生たちが連携して作り上げる「こどもみらい祭」。小学生が商品の製作から当日の販売まで手がける企画のほか、ミニゲームや製作体験など来場者が楽しめる企画も盛り沢山。学生たちは、子ども目線を意識した企画や運営の難しさと楽しさを体験しています。
- STUDENT'S
VOICE - お祭りを知らない子どもたちのために。
みんなで力を合わせました。
コロナでお祭りを経験したことがない子どもたちが増えている今、お祭りの楽しさを感じてほしい!そんな想いからスタートした今年の企画。代表なのに人前に立つことが苦手な私は、「温かい地連」や「わ(和・輪)」など、地連の真ん中にある想いを何度も呼びかけました。紙コップのベロベロおばけ、幸運のミサンガ、キラキラ花火のオモチャ。子どもたちが学生と協力して各売り場を盛り上げる当日の風景は、「温かい地連」の「わ(和・輪)」そのものでした。「また来たいです!」と笑顔で帰っていく子どもたち、来場者のみなさま、一緒に作り上げてくださりありがとうございました。


心理専攻4年
埼玉県 私立叡明高等学校出身
横山 いづみさん
PROJECT
05
クリスマスフェスタ
東京未来大学開学当時から続く伝統イベント
東京未来大学開学当時から続く伝統イベント

子どもたちと一緒に楽しむ
クリスマスを企画。
東京未来大学開学当時から続く伝統イベント『クリスマスフェスタ』。親子で楽しめる参加型のコンサートや、クリスマスの手作りワークショップなどを開催しています。なかでもコンサートは口コミで広がり、数日で予約が埋まるほどの人気ぶり。数年前からは、ワークショップなどの別企画も運営するように。学生にとっては、地域の方とのふれあいの中で、日々の学びを活かす実践的な場でもあります。
- STUDENT'S
VOICE - サンタさんが落とした手紙を探せ!
子ども参加型の劇、大成功でした。
学生劇には5人のサンタさんが登場。サンタさんの袋に穴が空いていて、子どもたちのお手紙を紛失してしまい大ピンチ。プレゼントを届けるためにみんなで奮闘する物語です。夏に構想を練りはじめみんなでブラッシュアップしてきたシナリオ。子ども参加型にしようというアイデアで、ますます面白くなりました。誰か一人が決めるのではなく、より良くするためのアイデアがたくさん出る所が地域連携推進委員会のいいところ。本番当日、会場内に散らばる手紙を一生懸命探す子どもたち。見つけた時の嬉しそうな表情。会場全体でワクワク楽しい時間を過ごすことができました。


こども保育・教育専攻3年
静岡県立 浜松大平台高等学校出身
大石 みきさん
-

-

-

-

- 在学生保護者の皆さんへ
- 在学生の皆さんが有意義な大学生活を送るため、教職員一同、支援させていただきます。
-

-

- 在学生の方へ
インフォメーションINFORMATION
- すべて
- ニュース
- イベント
- メディア
掲載 - プレス
リリース - フォト
ギャラリー